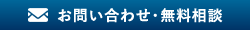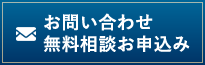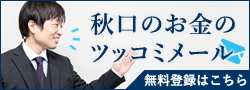- ホーム
- 事業の倍速コラム。
事業の倍速コラム。
個人から法人へ
2014/11/04
「会社にするのっていつの時期が良いの?」
こういった話は、個人のお客様からたまに覗います。
個人では対象のお客様と契約ができない(相手が取引先として認めてくれない)という場合や、
個人ではできない業種でない限り、個人事業のほうが基本的に簡単です。
では、どのような時に法人に移行するのか。
それはお客様の状況によって一概にいえないことも多いのですが、
①個人で3年目に入る前に法人に移行して、消費税の申告を後2年伸ばす。
②法人で申告したほうが、個人で申告するより税金が安くなる場合。
の理由が一番多いです。(私が税理士なのでという理由もありますが)
ただし、法人になったほうが、節税面でも色々できることが増えますが、個人であれば
許されていることで法人になったばっかりに許されてない部分もあります。
代表的なのは健康保険や厚生年金等の社会保険の加入です。労働保険は従業員がいれば必須のものですが、
厚生年金保険は個人の場合従業員が5人未満であれば強制ではありません。
(大雑把に書いておりますので、詳しくは社労士さんや年金事務所に確認して下さい。)
この社会保険料というのは恐らく人件費の次に支払う金額が大きなものです。
結局は、個人から法人になった場合のメリットと、法人になった時に発生するリスクや責任を
天秤に掛けて、どっちを選択するか経営者自身に判断してもらうことになります。
(法人の方が得するのはわかっているけど、個人の方が気楽だから法人にはならないという人も
おられますが、それはそれで正しい判断と思います。)
法人を設立してからでは遅いものだと思いますので、会社を作りたいと思った方は
まずは司法書士や税理士に相談してくださいね(^^
103万円の壁。
2014/11/17
毎年この季節になると、
「このまま働くと扶養からはずれてしまいますか?」
という質問をされることがあります。
いわゆる「103万円の壁」というものです。
103万円を超えると、働いている人に所得税が発生し旦那さん(又は奥さん)の配偶者控除が
無くなってしまい大きく損をするのではないかという思いからです。
確かに配偶者控除はなくなってしまいますが、かわりに配偶者特別控除というものがあり、
配偶者の所得に応じて控除することができます。
(当然、所得が増えればこの控除は減るわけですが。)
ですので、1円も税金を払いたくないという思いの方はともかく、
所得に応じて多少の税金は仕方ないとかんがえるのであれば、
141万円未満であれば多少なりとも控除はあります。
配偶者の所得が高いとその控除の効果も高いので、どっちが得だろう
という判断は必要かもしれませんが。
なら、141万円までならいいのかというと、別の問題(問題では無いんですけど)が出てきます。
これが130万円の壁というものです。
これについては次回に書きたいと思います。
あ、そうそう。
税金の話だと上記の通りなのですが、会社によっては「家族手当」をくれるところもあります。
この貰える貰えないの判定基準については会社ごとに違うと思いますので、確認してくださいね。
年末調整
2014/11/10
会社によってはもうそういう時期になっていると思います。
(まだ、配ってなかったり、説明してない得意先さんすいません(^^;))
必要なことを記入するほかに、いくつかの書類も提出するわけですが
(昔サラリーマンなりたての時は、保険に入ってなかったので住所と名前書いて判子押したら終了でした(笑))
基本的には
・生命保険控除証明書
・住宅取得控除関係の書類
で事足りるわけですが、
会社で健康保険等の加入されていない場合
(個人事業だけですよー 法人はダメですよー)
・国民健康保険の支払った明細
・国民年金保険控除証明書
というのも使えます。
最後に少し注意点。
会社側が言ってくれるとは思いますが、
今年に転職されている場合、源泉徴収票をもらっていると思いますが
(もらってなかったらもらってくださいね)
それも一緒に渡してくださいね。
そうしておくと、一緒に年末調整してくれるので確定申告の必要がなくなります(^^
無職期間が少しあった場合は、先ほど書いた書類の他にも社会保険関係で支払った領収書等も
あるかと思います。
控除証明書とダブってなかったらそれも使えますので、担当の方に確認してください。
130万円の壁
2014/11/25
前回は、所得税が発生するライン、103万円の壁について書きました。
今回は、130万円の壁についてです。
103万円を超えてしまうと所得税がかかりますが、一定の額までだと所得に応じた税金を払うだけなので、
働いた分ちゃんとお金は増えます。
しかし、配偶者さんが加入されている社会保険にもよるのですが、配偶者に扶養されている方が
扶養から外れると、個人で健康保険や国民年金に加入する必要がでてきます。
このラインが130万円と言われています。
国民健康保険は所得に応じて金額があがりますが、それ以外に1世帯に必ず払ってもらう平等割や
被保険者1人について払ってもらう均等割があり、加入した時点で所得に関係なく支払う金額があります。
(金額は住んでるエリアによって違います)
国民年金については1月15,250円と所得に関係なく発生します。
国民健康保険や国民年金は支払うのが義務ですので、本来であれは働いている方は既におさめているものです。
しかし、扶養に入られている方は、現状納めていません。
(そういうルールですので。親の扶養等に入られている人は年金の納付はあります。)
なので、いままで納めずにすんでいたものを納めることになり一気に手取りが減ってしまうのです。
このため、このラインを超えるなら一気に所得を増やさないと逆に手取りが減ってしまうことになります。
このルールを撤廃して女性にもっと働いてもらおうという話が今の国会ででています。
(選挙になってしまいましたので、色々延期になるのでしょうけど)
この制度が今後どうなるかはわかりませんが、働いている側の視点からですと、この壁を超えるか超えないか
は手取りに大きく左右することになります。
おおまかに書きましたが、国民健康保険や国民年金には免除申請等もあり、またその人の環境によって
違うこともあると思いますので、詳しくは配偶者さんが加入している社会保険の人に確認してみたり
社労士さんに聞いて下さい。
- 2021/06
- 2021/05
- 2021/03
- 2021/02
- 2021/01
- 2020/12
- 2020/11
- 2020/10
- 2020/09
- 2020/08
- 2020/07
- 2020/06
- 2020/05
- 2020/04
- 2020/03
- 2020/02
- 2020/01
- 2019/12
- 2019/11
- 2019/10
- 2019/09
- 2019/08
- 2019/07
- 2019/06
- 2019/05
- 2019/04
- 2019/03
- 2019/02
- 2019/01
- 2018/12
- 2018/11
- 2018/10
- 2018/09
- 2018/08
- 2018/07
- 2018/06
- 2018/05
- 2018/04
- 2018/03
- 2018/02
- 2018/01
- 2017/12
- 2017/11
- 2017/10
- 2017/09
- 2017/08
- 2017/07
- 2017/06
- 2017/05
- 2017/04
- 2017/03
- 2017/02
- 2017/01
- 2016/12
- 2016/11
- 2016/10
- 2016/09
- 2016/08
- 2016/07
- 2016/06
- 2016/05
- 2016/04
- 2016/03
- 2016/02
- 2016/01
- 2015/12
- 2015/11
- 2015/10
- 2015/09
- 2015/08
- 2015/07
- 2015/06
- 2015/05
- 2015/04
- 2015/03
- 2015/02
- 2015/01
- 2014/12
- 2014/11
- 2014/10
- 2014/09
- 2014/08
- 2014/07
- 2014/06
- 2014/05
- 2014/04
- 2014/03
- 2014/02
- 2014/01
- 2013/11
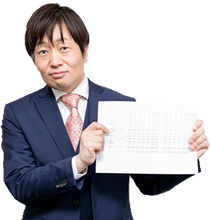
まずはお茶でも飲みに来ませんか?
そして、社長の考える未来と現状を教えて下さい。
税理士に相談!みたいなお固い感じじゃなく、気軽にお茶でも飲みながら、今の経営のこと、将来の夢などを語りに来てください。相談料は不要です。
ご希望の方には、秋口特製の『未来こうなるシート』を後日お送りします。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階 事務所概要はこちら