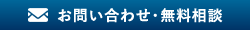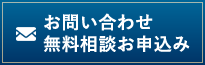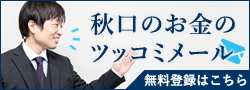事業の倍速コラム。
- 税務顧問 2021/05/28 保証解除
- 2021/05/27 2代目の憂鬱 その2
- 2021/05/26 2代目の憂鬱。
- 2021/05/25 社長自身が売上が全てと言い出すと。
- 2021/05/24 売上至上主義からの脱却。
- 2021/05/20 先のことはわからないけど。
- 2021/05/19 従業員の雇用といえば
- 2021/05/18 従業員の雇用
- 2021/05/17 時間は先に確保する。
- 2021/05/14 何をするか、いつするか、いつまでにするか。
- 2021/05/13 比較対象にするのは、計画か、過去の実績か
- 2021/05/12 速報値の大事さ。
- 2021/05/11 税金対策の前にすべきこと。
- 2021/05/10 なぜコーチ型と名付けたか。
- 2021/05/07 リアルタイム業績把握の大事さ
- 2021/05/06 ホームページの更新
保証解除
2021/05/28次の代に移すとき、それは親子や従業員や外部であった時に
「借入の保証人」
といった事が問題になる事があります。
M&Aの場合は、買い手が資金に余裕があれば、返済してしまえば良いのですが、
親族や従業員ではそういった事が厳しい事が多いです。
先代には不動産があっても、親族・従業員には担保となる不動産があるとは限りません。
なんとか、今の保証を次の代には引き継がずに承継をしていきたい。
こういった時に使えるのが
といったものです。
条件はそれなりに厳しい
誰でも使えるのなら、全ての保証がなくなっているはずです。
知っている人が少ないと言うのもありますし、金融機関としてはしたいものではなりません。
ただ、金融機関としても、国(金融庁)から言われている手前、ほったらかしにするわけにもいけません。
では、なぜ浸透していないか。
それは、条件がそれなりに厳しいと言う一点です。
会社として正しい姿であれば問題がない・・・のだが。
細かくは、実際にするときに調べてもらえれば良いんですが、
ざっくり言うと
・公私混同していない。
会社のお金と個人のお金が混ざっていない。なんか当たり前のように聞こえますが、中小企業でできているところは
実際は少ないです。なんでそんな事しないといけないねん。ってぐらいの経営者さんすらおられる始末です(^^;
金融機関としては、会社か個人かわからないところに、リスク100%では貸せないと言う判断ですね。
・黒字である。
借入金の返済は、利益が出てないと返済できません。
赤字が続いているような会社にはお金が貸せないと言うわけです。
これも当たり前のように思いますが、実際には黒字の会社と言うのは少ないのです。
そして、この両方をちゃんとできている会社は・・・製造業のように大きな投資が必要な会社でないかぎり
お金借りてないんですよねぇ。お金があるんで。
言い換えれば、お金が借りれない危ない会社は、
・公私混同していて
・赤字である
と言う事になります。
自分の会社がどのような状況にあるか。
お金が保証人無しで借りれるかどうかで一度判断してみてはいかがでしょうか?
2代目の憂鬱 その2
2021/05/27昨日は主に先代の問題点を挙げてみました。
今回は2代目自身の考え方を挙げてみます。
新しい事にチャレンジしてくれない。
・代が変わったので大きな事をしてみたい。
・アナログからデジタル化していきたい。
など、先代が手をつけなかった問題点であったり、新しい事にチャレンジしたくなると思います。
ただ、今までしてきた事を変える試みについては、なかなか対応してもらえません。
生返事であったり、返事はあったものの実際にはほとんど動いていない。
こんな事もあるかと思います。
ただ、2代目だからかといえばそうではありません。
先代だろうと、従業員は新しい事をする事については懐疑的です。
人間、基本的には変化を嫌うものなので。
ただ、2代目の場合は、言い訳に「先代はそんな事言わなかった。」と言うワードが使いやすい。
と言うだけです。
新しい事をするには小さな成功体験から。
新しい事をする場合、小さなロットでする事をお勧めします。
失敗してもロスが少ないと言うのもあるのですが、新しい事をする事に抵抗のない人を数人集めて、少しづつ初めて成功体験を増やしていく。
そして巻き込む人を少しづつ増やしていって「新しい事」から「当たり前の事」にシフトチェンジしていく必要があります。
今流行のDX(デジタルトランスフォーメーション)も、一気にするのではなく、
一部門から、一部からといった浸透方法が一般的になってきていますね。
今はやり・・・ってほど、浸透しているかは微妙ですけど。
2代目の憂鬱。
2021/05/26先代から会社を引き継ぐ。
次世代に会社を引き継ぐ事ができると言うのは大変素晴らしい事だと思います。
事務所が京都にあるからか、割と何代も続いている会社があったりするのですが。
先代の影響が抜けていない。
親が亡くなって承継された場合には色々な困難が待っていますが
元気な時に交代した時にも色々問題が出てきます。
その一つはお金に関する決定権です。
外部の人間はお金の決定権のある人に寄り添う必要があります。
会社の借入金の担保が親(先代)の財産であった場合、金融機関は社長より先代に権限があると判断します。
先代の影響があるかぎり、実際に引き継いだとはいえません。
先代が会社離れができていない。
先代が初代だった場合、会社への思い込みが強いのと、仕事一筋だったので引退後にする事がないのもあり
頻繁に会社に行く方も多いです。
行ったら行ったで口を出してしまう。
親族の承継の場合は、事前に準備期間が十分ある事が多いので、一度譲ったからには呼ばれないかぎり行かない覚悟
も必要になります。
親族間の引き継ぎであっても、引継ぎを受ける側だけでなく、引き継ぐ側にも覚悟が必要になります。
社長自身が売上が全てと言い出すと。
2021/05/25スタートが素晴らしく良い社長のうち8割ぐらいは、売上を取ってくる事がとてもうまい社長です。
たまたま、この業界でスタートしているけど、何を売らせても確実に取ってくる。
よく聞くのは、とりあえず注文を取ってきたは良いけど、
その後のやり方はわからないから誰かに聞いて実際に納入まで終わらせる事ができる人材です。
公私が混ざりがち。
売上を持ってくる人の多くは、公私を普段からあまり気にされません。
自分が納得さえすれば、夜遅くまで働くことも、休日働くことも気にしません。
なので、普段の生活の仕事とプライベートの垣根がない事がほとんどです。
こういった人は経費も事業の経費なのか、プライベートな物なのかの判断がつかない事が多いです。
本人は、なんでも仕事で使っているつもりですが、客観的に見れば違ってきます。
判断がだんだん緩くなってくると、無駄な費用が増えてくることになります。
言い訳がうまい。
売上を取ってくる社長は基本的に口がうまいです。
響きが悪いので、コミュニケーション能力がずば抜けて高いと言い換えても良いのですが、
言い訳がうまいともいえます。
得意先からクレームがあれば、まずお詫びから入られますし、言い訳をして拗らせるような事はしないのですが。
お金を使う事、使う理由に対する自分への言い訳がうまいです。
この費用は必要であった理由、使わないといけない理由を並べてきます。
こちらとしては、何言われても無理なものは無理なのですが、どこまでも根拠として話をされてきます。
その話自体の合否はともかくとして、
言い訳をしている=普通なら認められないものである
事を経営者自身が認識しているからの言い訳です。
本人も理解しているのですが、なんだかんだと自分に甘くなってついつい使ってしまう。
こういった事をしていくと、最初の数年は順調な滑り出しであっても、5年後ぐらいに会社が一気に傾くことになります。
売上を上げるのには、人とお金が必要になってくるので、一人の限界を超えるぐらいで一旦落ち着きますが、
人間の欲望に落ち着きはないのと、売上を上げるための本来の経費も増えてくるので、会社が破綻に向かってくるのです。
お金に節度のある経営者さんと付き合ってたりすると、自覚も出てくるのですが、同世代の元気な社長だとお金の使い方も
荒いので、ついついといった事が起こりがちなのも 売上を取ってくることに自信がある社長の特徴ですね。
売上至上主義からの脱却。
2021/05/24売上は会社の根幹となるものですので、一番大事なものになります。
ただし、赤字になってまで追いかけても意味がないのは理解されるかと思います。
が、この赤字というラインが人によって全然違ってくるのが不思議なものです。
経費がかさみがち。
社長であれば全体の数字を見る事があるので理解されている事が多いのですが、
営業マンだと、
「原価を超えなければ利益は出ている。」
という判断になりがちです。
会計で言うと売上総利益(粗利)ってやつです。
それより下の経費については普段営業マン自身が見ているわけでは無いので判断しづらいのが現状ですが。
営業マン本人の人件費、間接的に手伝ってもらっている人の人件費や、移動等の経費色々差し引いての利益です。
無駄に他の経費がかかってしまえば、逆に負担にしかならない。
常にその部分を理解してもらう必要があります。
使途不明金が目立つ
決して、何に使ったかわからないお金が出てくるわけではなありません。
費用対効果が分かりにくい。ノベルティ・飲み代等が増えてくる事が多いです。
相手との関係性を継続させるために必要で・・・と言いつつ、仲間内で単に楽しんでるようなものです。
昔からこの手の費用は出てくるので、担当の変更や移動で対処しているのですが、それはそれで先方から
「前の担当はしてくれたのに・・・」
といった困った対応も増えてきたりします。
経営は全て効率だけで進めるわけでは無いですが、締めておかないと、緩む方向は無限大に広げられますので。
簡単に赤字に転落します。
先のことはわからないけど。
2021/05/20前回に人の話をしていましたが、継続的に仕事をお願いする時に人を雇用するということになると
基本的にはその人が退職されるまで雇うことになります。
ということは、退職されるまで会社を継続する必要が出てくるわけです。
となってくると、高齢の人を雇わなければ、10年、20年と会社を継続する必要が出てきます。
20年後の未来を予測することはできませんが、自分の目的を決める事はできると思います。
自分のしたいこと。
例えば20年後にどうしていたいか。
渋いおじさまになっていたい。と言ったスタートであっても、
・渋いおじさまはどのような地位にいるのか
・渋いおじさまはどのように扱われているべきか
・渋いおいさまはどのぐらいの稼ぎが必要なのか
と考えてみてればイメージが湧くかと思います。
会社の20年後を考えるのに渋いおじさまスタートはどうかとは思いますが、
イメージしやすいのは自分自身のことだと思いますので、きっかけはなんであれ先のことをイメージし、
会社のことなので、数字化していきます。
理想の売り上げ、費用、利益、従業員数、支店数や店舗・事務所の平米
具体的にできればできるほどイメージがしやすいです。
目標が決まれば、今することは自ずと決まる。
先の目標(別に10年後でも5年後でも良いんですけど)が決まれば、その目標のために今しないといけないことは
自然と決まってきます。
今すべきことは、先の目標がないと決めにくいです。
例えば税金を減らしたい時に、その減らし方も先が決まっていれば取る手段は変わってもきます。
従業員の雇用といえば
2021/05/19従業員を雇うかどうかは悩むもの。
一旦雇うと、固定費がかかりますし、簡単にやめてもらうわけにもいきません。
昔とは違うとはいえ、従業員とその家族の生活を引き受けることになりますし。
しかも、外部の人間に依頼するというのは昔に比べて簡単になっているかと思います。
それでも敢えて従業員を雇う必要を考えてみると。
経営目標を共有できる。
外部の人に、仕事を依頼する。
他の経営仲間と提携して事業を展開していく。
便利であったり、楽しくはあるのですが、目標を共有して進めていくのには向いていません。
提携であっても、それぞれの目的が合っての提携なので、目標の共有とはずれていくかと思います。
従業員であれば、社内の仲間として一緒に目標に向かって進めていくことが基本ですので
経営目標の共有は比較的しやすいです。
(それはそれで、経営者の力量が問われるのですが)
長期スパンで付き合うことができる。
ずっと付き合っている、仕入先、業者さん、経営仲間というのは確かにあります。
ただ、会社として長期に最後まで付き合ってくれる一番の人は従業員です。
会社の色に育ってくれれば、一番の戦力であり仲間になってくれます。
まず、自分の事業をいつまでするか、最後どうしたいのか。
ここさえ決まってくれば、人を雇うのか雇わないのかは自ずと決まってくるのではないかと。
従業員の雇用
2021/05/18一人で事業を展開を進めるには限界があります。
なので、人を確保することが一般的になってきます。
人を入れるのか入れないのか。
まず、今後の事業の展開で人が必要なのか。
必ずしも必要とは限りません。
一人でも大きくすることは可能ですし、そもそも必ず大きくする必要もないので。
あとは、人の雇用という選択以外にもありますので。
それは外注です。上下関係が無い言い方をすれば提携とも言いますね。
今は副業が当たり前になっているようですので、アルバイトとは違う形で自社の仕事の特定の分野についてお願いします。
従業員ほどこちらの融通が効くかは相手次第です。
契約書等は交わすものの、秘密保持の点では不安な部分もあるかもしれません。
やってほしいときに、先方が暇かもまたわかりません。
ただ、不要なときにはお金は発生しないというメリットもあります。
人を入れるなら我が身を律する。
人を雇用することがあるなら、
従業員は思っている以上に経営者の行動を見ていますので、
・経費の私物化
・従業員に対する言動と自分の行動の違い
などがあれば、思っている通りの仕事はしてくれないかもしれませんね。
ま、相手も人間ですので、理不尽だと思えば会社のためとは思いにくいでしょう。
人間まず自分の身が一番ですので。
律してやっとスタートに立てる。そんな感じです。
自分が従業員時代にどんな事を思っていたか。
思い出したら、イメージがつくかと思いますよ。
時間は先に確保する。
2021/05/17経営者といいつつ、常に現場にでることが多い、中小企業の社長さん。
経営のことを考えたいところだが、現場にいれば現場の仕事が終わらない。
だから時間がない。
いつか時間ができれば・・・といっている間は永遠に時間はできません。
それは、仕事は作ればいくらでもあるから。
なので、人と会うことで無理にでも時間を作る方法をとります。
時間を確保する。
人と会うといっても、知人の社長と会ってもなかなか経営の話になりません。
同友会やいろいろな会合に参加することで経営を考える事もできますが、
具体的な自社の数字をつかってすることはありません。
そこで、出来上がった試算表をもって税理士と話すことで、経営を考える時間を確保していきます。
人に話すことで自分の考えが整理される。
無理やり作った時間ですので、話すことを事前に考えておくことは難しいかもしれません。
しかし、顧問税理士相手にかしこまって話す必要はありません。
自分の思いつきで話せばいいと思います。
現状を確認して、自分でわかっていても言い訳を話してみて、そこからヒントになることが
意外と出てくるものです。
頭で考えるより、文字にしたほうが良いことが多いですし、誰か他人に話を聞いてもらうだけで
するべき事が思いつく。
都合のいいように思いかもしれませんが、解決策は経営者の頭に元々入ってることが多いですよ。
税理士側もヒントは出せますので。
何をするか、いつするか、いつまでにするか。
2021/05/14昨日は、計画と比較するのか、前年と比較するのかと聞きながら、両方比較してねという話でした。
差異があり、その原因がわかった。
そこで満足しては意味がありません。
そこからどうするか。
今後の行動を考えていく必要があります。
変える?変えない?
計画通りであれば、変える必要はありません。
計画と違っていても、翌月までこのまま進めても問題がない場合も変えることはありません。
計画と差があり、このまま進めても目標に到達しない場合、
これは何かを変える必要があります。
・自分の行動を変える
・内部の人間に指示を出す
・外部の人間にお願いする
・なにか新たな出費をする
色々考えられると思います。
実行できるかはとりあえず置いといて、思いつく限りリスト化するのが一番です。
後で削ればいいんで。
何をどれだけいつまでに
このときに、
何をするか(何をしないか)も大事なんですが、
・どのぐらい(期間・金額)
・いつまでに(期日)
まで考えないと、なんとなく日々が過ぎてしまいます。
せっかくの早めの行動をしていくのに、間延びした行動をしてしまっては意味がありません。
一人でも考えて行動することはできるのですが、自分だけで考えると堂々巡りすることもあります。
考えてるだけでなかなか行動できないのが人間ってものです。
・社内で考えて宣言する。
・仲間と考えて宣伝する。
・税理士と考えて行動する。
人に話すと自分の考えもまとまりますし、人に宣言するとやらないと行けない気分になるものです。
誰かに話す。
一番簡単で一番効果があります。
比較対象にするのは、計画か、過去の実績か
2021/05/13速報値がでたとして、数字を見ただけでは、良いか悪いかわかりません。
何かを比較して初めて判断ができます。
年初計画との差異
年初計画との差異は
・計画通り進んでいるのか
・どこに問題若しくは予定以上の効果が出ているのか
という判断材料になります。
計画との差異なので、計画より悪い場合も、良い場合も差異を見て、改善する必要が出てきます。
悪い場合
予定通り進んでないわけですが、どこがネックになっているのか洗い出していきます。
計画通りどうしても進まないのであれば、修正することも検討すべきですが、基本的には
目標達成のために改善策を考え行動していきます。
良い場合
計画通りでも同じなのですが、良い原因が、未来の先食いなのか、計画が比較的容易だったのか
の判断をしていきます。
計画より良かったらこのままで良いやん。
という訳ではありません。良い原因を探って、その良い部分を更に推し進められるものであれば
計画を上方修正することも検討しなければいけないからです。
なぜか?
計画の作成が間違っている可能性もあるからです。
過去の実績との差異
基本的には、前年の同月との比較が多いです。
季節によって売上・経費の変動がある業種が多いので、前年の同月とが一番比較しやすいです。
単純に去年より良いか悪いか、どの部分が良いか悪いか。
良いほうがいいんですけど、計画のたてかたによっては経費の増加や売上の減少が出てくることもありますので、
悪いからと言って駄目ではなく、原因を探すことが大事になります。
原因がわかっているものであれば、悪くなっていても問題はありません。
ただし、予想の範囲内であれば、ですが。
タイトルの回答としては、両方ということになります。
速報値の大事さ。
2021/05/12急いで業績を調べてみても正しいかどうかわからない。
そんな数字使っても、正しい判断ができるのか?
そんな不安もあるかと思います。
殆どの数字は、月末までに確定している。
・売上って、請求書作成する前にわかってますよね?
何かすらに集計されている人がほとんどです。
日々の売上が上がる業種(飲食とかアパレルとか)であれば今はポスレジを
使われているところがほとんどなので、いつでも把握することができます。
・原価は日々わかる場合もありますし、請求書までは間に合わなくても、納品書・見積書
などで対応することが可能です。
・経費の殆どは、通帳から落ちているか、カードから落ちていますので、データを吸い上げれば
特になにかをすることなく集計することが可能です。
仕組みが足りなければ、作ればいい。
と、言っても速報値にするにも足りない場合もあるかと思います。
その時は、速報値として十分な状態になるように日々の処理は集計方法などを
御社の負担がない、もしくは負担が少ないように作っていけばいいだけだと思います。
税理士事務所でやっていることすら、ベストというわけではありません。
いくらでも改善できることがあります。
もし負担になることがでてきても、他で改善すればいいだけですので。
それに一番必要な改善は、集計でも会計でもなく会社の事業ですので、
業績の把握はそのための手段の一つにすぎません。
税金対策の前にすべきこと。
2021/05/11税理士に頼んでるのは税金対策のため。
って話もよく聞きます。
別に間違っているわけではありません。
税金は払うべきものではありますが、無駄に払っても仕方ないものです。
国との関係はともかく、1企業であれば、費用の一種に過ぎません。
税金であれ費用であれば、必要以上に払うことは企業として問題とも言えます。
税金を払いたくないという流れは、
税金を払いたくない=お金が減るのが嫌だ
お金が減るのが嫌なのはなぜなのか。
1)なくなると会社が潰れるから
2)他に使いたいことがあるから
この2つが大きな原因ではないでしょうか?
なくなると会社が潰れるから
お金がなくなると会社は潰れます。
どんだけ利益を出していてもです。
本来利益を出していれば潰れないんですけど、
1)売上の回収が支払いより遅い
2)借入の返済が会社の器を超えている。
といったことが原因です。
決して税金を払うから潰れるわけではありません。
言ったところで誰も納得しないのですが、税金は利益からしか取りませんので。
消費税も預かっている以上のものを払うことはありません。
要は事前にわかるようにしておけば問題は出てこないわけです。
他に使いたいことがあるから
確かに、やりたいことは色々でてくると思いますし、そこにはコストがかかります。
しかし、先程書いたように税金は利益からしか取りません。
では、使いたいことをした後であれば自然と税金が減ることになります。
大きなものを買った場合は、いっぺんに利益を減らしてくれませんので事前に検討が必要ですが
ある程度予測さえ立てて行動すれば
・やりたいことをして
・税金も減らせる
ことになります。
簡単に言うと投資は税金減少につながるわけです。
基本的には、通常の節税=税金の先延ばし(もしくは一定の貯蓄)ですので、
使いたいことに使った後に、一定の貯蓄として節税をするのが一番になります。
使いたいことに使う=会社の未来のために投資する。
ことになります。
先のことを考えて動かないと、
なにもしないで税金を払っておいたほうがお金が残ってた。
なんてことになりかねないので、明確なビジョンを持つところから始める必要がありますね。
なぜコーチ型と名付けたか。
2021/05/10私達の対象のお客様は基本的には経営者さんです。
・自分が考え
・自分が行動し
・自分が責任を持つ
こう書くと、責任の重い職種です。
良いことも、悪いことも自分で受ける仕事になります。
言い換えると、自分で責任を取るなら何もしなくてもいいわけです。
ご飯が食べれない状態であれば、何もしないってことはありませんが
ある程度自由がきくので、サボりがちになるときもあります。
そこで、税理士が常に見ることで、一定の緊張感を持ってもらう意味も込めて
コーチ型と名付けました。
現状の説明後、自分がどうすべきか考えるだけではなく宣言する。
年初に考えた計画を今の時点でどれだけ実行できているでしょうか?
殆どの人は、
立派な計画を作ってはみたけど、特に実行していない。
なんてことになっているのではないでしょうか?
理由は簡単。
誰にも伝えてないから。
従業員には会社としての目標、個人としての目標を作るものの、
経営者としての目標を具体的に対外的に言う経営者はあまり見かけません。
上場企業の社長であれは、株主の目もありますので、宣言されますが
経営者=株主である中小企業では、株主の監視機能は効きません。
そこで、数字を常に見ている税理士に宣言してもらうのです。
宣言に対して、動いたかどうかをチェックし、動いてなければ動くように促す。
全く税理士の仕事ではありません。
正直、顧客に対して嫌がることも言わないといけないわけです。
(税務上の問題はそれ以前に話しますけど)
経営者がどういう人物であるかもコーチ型税務顧問では確認する必要が出てきます。
経営者として、嫌なことを言われても前に進む気力があるのか。
せっかく独立して自由になったのに・・・と思われる方もおられると思います。
それでも今の状況を打開するために、やってやるぜ。
そういう人に対して、こちらも本気で付き合う。
そういったサービスになっています。
リアルタイム業績把握の大事さ
2021/05/07リアルタイム業績把握。
なんか逐一業績をチェックするイメージです。
・飲食店で来客が少ないので外で呼び込みをする。
・パン屋さんやケーキ屋さんで、販売数を見て昼からの製造を調整する。
といったイメージでしょうか?
それも大事なことではありますが、そうではなく
先月の業績を最速で確認し、今月に活かす。
と言った、ある程度大きな会社であれば当たり前のようなことを指しています。
なぜ、そんなに急ぐのか。
中小企業の多くは
・数ヶ月に一回、もらった資料の説明を受ける(既に2・3ヶ月前のもの)
・月に一回、試算表が送られてくるが、月末に郵送されるので既に1ヶ月前の内容である。
・年に一回、決算だけしてもらって業績を知る。
といったパターンで業績を把握しています。
当然、一番気になる部分(多くは売上)は毎月確認されているのですが、それ以外には興味がない
人が多かったります。
それだと、例えば
・原価を確認してなかったばかりに、思ったより利益が出てなかった。
・売上を伸ばしたのはよかったら、残業や経費が予想以上にかさんでいた。
といった事業が傾くものや
・利益が予想以上に出ていたが、決算月直前で気付いたので、したかった投資が
決算に間に合わず、税金を減らすことができなかった
などという、利益が出たものの、うまく活用できないって事もでてきます。
業歴が長い会社さんは自社で毎月確認し、状況を判断されるクセを持たれている
経営者さんが多いです。
リアルタイム業績把握
当月末日に当月末のデータを揃えるのは、中小では厳しいもの。
しかし、中小ならば、5-10日以内に業績を把握することは規模が小さいだけに
割とできたりします。
そこで、当事務所と一緒に
・毎月最低限必要な資料はなにか
・どれだけ手作業をせずに進められるか
・如何に最短で業績を把握できるようにするか
といったことを作り上げ、毎月業績を把握し、話し合う環境をつくる。
ところから始めていきます。
把握しても、考え、行動しないと意味がありません。
それは次回以降に書きたいと思います。
ホームページの更新
2021/05/06今年の目標の一つである、ホーページの更新をなんとか終えることができました。
と言っても、これで終わりではなく、これからが頑張っていかなければならないところです。
新たな挑戦
・ただただ税理士として申告書だけ作っていてもいいのか(これも当然大事)
・お客さんに元気になってもらわないと、自分たちも元気にはなれない。
・コロナ過ではあるものの、コロナだからとなにもしないわけにいかない。
・お客さんに元気になってもらわないと、自分たちも元気にはなれない。
・コロナ過ではあるものの、コロナだからとなにもしないわけにいかない。
今までは、会計監査と税務を本業とし、
お客さんと話している中で気になったとこと、伝えたいことを伝えるという
受け身なアドバイスをしてきました。
しかし、それでは対応が遅かったりします。
経営者は反射的に行動することが多いからです。
そこで、お客さんに対するおせっかいを一段回上げることにしました。
本気のお客さんには、本気で返す。
お客さんといっても、目的は色々。
・安定しているので、最低限だけでいい。
・会計とか申告とかわからないから、わからないところは聞くから教えてほしい。
といった会社から
・上に上がるにはどうしたらいいか、なにからすればいいか細かく教えてほしい。
・具体的にどうしていいか一緒に考えてほしい。
・もっと会社の中に入ってほしい
といった会社まで。
会社の経営者というのはわがままなもの。
従業員には向いていないから代表している。
こんな人が多かったりします。
別に問題があるわけではありませんし、私もその部類です。
が、その中でも人に意見を求め、自ら変わるべく努力をしてくれる。
そんな経営者もおられます。
自分も気づいているけど、見たくなかった、そういう部分に触れたとしても対応する。
そんな、本気な経営者に対し、最速で深くまで付き合おうと考えました。
「コーチ型税務顧問」
こんなタイトルで進めていきます。
当然、今までのお付き合いで十分という人は、今まで通りよろしくお願いいたします。
コーチ型の税務顧問ってなんやねん。
と思われるかと思います。
それはぜひともホームページを読み進めて・・・と言いたいですが、
少しずつブログにも書いていきたいと思います。
- 2021/06
- 2021/05
- 2021/03
- 2021/02
- 2021/01
- 2020/12
- 2020/11
- 2020/10
- 2020/09
- 2020/08
- 2020/07
- 2020/06
- 2020/05
- 2020/04
- 2020/03
- 2020/02
- 2020/01
- 2019/12
- 2019/11
- 2019/10
- 2019/09
- 2019/08
- 2019/07
- 2019/06
- 2019/05
- 2019/04
- 2019/03
- 2019/02
- 2019/01
- 2018/12
- 2018/11
- 2018/10
- 2018/09
- 2018/08
- 2018/07
- 2018/06
- 2018/05
- 2018/04
- 2018/03
- 2018/02
- 2018/01
- 2017/12
- 2017/11
- 2017/10
- 2017/09
- 2017/08
- 2017/07
- 2017/06
- 2017/05
- 2017/04
- 2017/03
- 2017/02
- 2017/01
- 2016/12
- 2016/11
- 2016/10
- 2016/09
- 2016/08
- 2016/07
- 2016/06
- 2016/05
- 2016/04
- 2016/03
- 2016/02
- 2016/01
- 2015/12
- 2015/11
- 2015/10
- 2015/09
- 2015/08
- 2015/07
- 2015/06
- 2015/05
- 2015/04
- 2015/03
- 2015/02
- 2015/01
- 2014/12
- 2014/11
- 2014/10
- 2014/09
- 2014/08
- 2014/07
- 2014/06
- 2014/05
- 2014/04
- 2014/03
- 2014/02
- 2014/01
- 2013/11
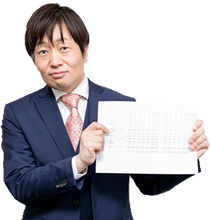
まずはお茶でも飲みに来ませんか?
そして、社長の考える未来と現状を教えて下さい。
税理士に相談!みたいなお固い感じじゃなく、気軽にお茶でも飲みながら、今の経営のこと、将来の夢などを語りに来てください。相談料は不要です。
ご希望の方には、秋口特製の『未来こうなるシート』を後日お送りします。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階 事務所概要はこちら