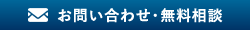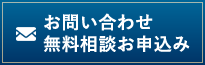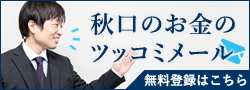事業の倍速コラム。
- 税務顧問 2021/06/30 法人の信用力。
- 2021/06/29 法人の活用法
- 2021/06/28 個人か法人か
- 2021/06/25 サブスクリプション
- 2021/06/24 運転資金と設備資金
- 2021/06/21 お金の動きがわからない。
法人の信用力。
2021/06/30法人は個人と比較して、信用力が高いと言われます。
なんとなく、個人より法人の方が規模が大きそうだから信用力が高いのでは?
と言うわけではありません。
法人は規模が大きいから安全なのか。
金融機関から見た場合、
個人と違い、法人には資本金がありますので資本金が多ければ、確かに信用力は高いと思います。
後、個人より法人の方が会計がしっかりしている事が多いので、法人の決算書の信用度は高いといえます。
ただ、資本金が大きくなければ、開業したての法人も、個人も同じように信用は低いですし、
しっかり稼いでいれば、個人も法人も信用はあります。
得意先との関係
基本は、人と人との繋がりや信用から始まる事が多いのですが、上場企業のような先と取引をする場合
法人に限定されている事も多いです。
単発で取引する場合はともかくとして、継続的に取引する場合、相手も簡単になくなってもらっては困るので
一定規模である事も求められます。中には、決算書を提出させる先もあります。
それはともかく、業界によっては法人である事が今後の事業の拡大に必須の場合も出てきます。
最終的には人間性とはいえども、一定規模を超えると最終決済までに何にもの人間の許可が必要になりますし、
そのときには、多少の形式が必要になってくるので、自分のする事業の将来を考えて設立も考える必要があります。
法人の活用法
2021/06/29個人事業ではなく、法人を作るメリットは何か?
税金や国民健康保険のコストダウン以外のメリットを考えてみましょう。
お金に関係するもの。
コストダウンとほぼ同義ではありますが以下のことがあります。
・自分で給与(役員報酬)を取れる
個人では、設けたお金から税金を引いたお金は自由に使って構いません。
しかし、法人は、社長個人とは別の存在なので、他の従業員と同じように、給与をとってお金を得る必要があります。
役員報酬の金額をベースに、給与所得控除や社会保険料の恩恵を受ける事になります。
・退職金も取れる。
個人事業では、給与も取れないし、自分の退職金も自分の事業から取る事はできません。
(小規模企業共済をつかって退職所得を得る事は可能です)
法人であれは、自分に退職金を支出する事ができます。
小規模企業共済の継続も可能です。
お金に関係しないもの
・他人の出資を受けられる。
後で面倒が起こる事も多いですが、大きな会社は一人の資本から成り立っているのではなく、
何人かの(上場企業ならそれこそ何万人?規模なんでしょうけど)出資で成り立っています。
代表が必ずしも株主である必要もありませんし。
大きな規模、大きな事業をするには大きな資金が必要です。
研究開発関係であれば、自分一人の出資で開発する事はほぼ不可能だと思います。
・何人かの仲間で事業を展開する。
必ずしも一つの会社で何人も役員がいる必要はありませんが、仲間は多い方が大きく事業を展開できる
可能性が高まります。
個人事業であれば従業員として雇用するしかありませんが、会社であれば、役員として共同経営する事も可能です。
お金に関係しないものは、法人を作る本来の目的です。
小さい会社を作るときに、何人もの役員、何人もの出資者だと揉める事が多いですよと
言うことにはしていますが、夢と希望と野望で手一杯なお客さんは聞いてくれません(^^;
次回は、本来の目的以外での優位性を探っていきます。
個人か法人か
2021/06/28ある程度の規模を考えている場合、個人事業主という選択肢はあまり考えられていません。
特に、何人かで組んで事業を進める場合は、個人事業主では自由度が少ないからです。
個人事業の必要性
別に、今個人事業主をしている人を否定しているわけではありません。
私も個人事業主ですし。(税理士って法人化するのに、資格者2名以上いるんです)
なぜ、個人事業が選ばれているか。
多くは以下の理由ではないでしょうか?
・開業が簡単
・簡単な会計制度が使える。
・規模が小さい場合、税額が会社より低い
・従業員雇っても、社会保険が必須ではない。
コストが安い間は、個人事業で十分。
よく、法人成り(個人事業から法人(会社)に変更する事)にするタイミングを聞かれます。
最大の理由は、社会保険・税金を含めたコストの違いですね。
一定の所得を超えてくると、所得税等の税金+国民健康保険料の金額が法人より個人の方が高くつきます。
そこまでは、個人で十分と言えるわけです。
とは言いつつ。
小さい会社もやはり多いもの。
では、なぜ会社を作ったのか、会社を作ることによるメリットを、税金や国民健康保険料以外の角度から
次回は見ていたいと思います。
サブスクリプション
2021/06/25経費の削減ってときに、一番ちぇっくするのは毎月の引落しされているもの。
その中でも、最近流行りの「サブスク」なんて言い方すら古いでしょうけど、昔からあるものの一つです。
定期購入や月会費と言われるものがそうですね。
知らない間に固定費として滑り込まれている。
毎月引落しされているものなら、経費を見直すときとかに確認することができます。
(それも頻繁にはしませんけど)
これが、携帯電話のように変に年縛りがあったり、年払いになっていると・・・・
「また、次の機会に」
という流れになってしまいます。
毎月自動引き落としになるようなものは、契約時に特に注意する必要があります。
解約方法がわからないなんてこともよく相談に受けますので。
収益としては、一番ありがたい。
なんで、昔からあるのか。
それは、収入を得るものに取っては非常にありがたいからです。
・定期的な売上が見込める
・将来の予測が立ちやすい
・一回入ってもらうと、継続性が高い
当然、価値がないと感じられたら蹴られてしまいますけど、惰性で払ってるものって
意外とありますよね?
一方では面倒なもの、厄介なもの。
逆から見れば美味しいもの、便利なもの。
いろんな角度で考えたいものです。
運転資金と設備資金
2021/06/24前回、少し運転資金の融資について書きました。
銀行が出している、借入の商品は色々ありますが、事業関係で大きく分けると
・運転資金
・設備資金
に分けられます。
運転資金
事業拡大してきたときにお金の動きが大きくなってくると、残高の心配が出てきます。
何か一つのズレが資金ショートにつながるからです。
先払いの仕事の場合、ある程度現金をプールして置かないと仕事を受注することもできなくなります。
こういった場合に使うのが運転資金です。
借入限度額も小さめで、借入期間も次の設備資金と比較すると短いです。
使用理由が通常の事業の費用に使うものですので、借りるときに見積もりを必要としないことが多いです。
そのため、設備で借りてもいいものも運転資金で借りてしまうような事があったりします。
お金は、借りるなら大きく、期間は長くが会社が生き残る基本となります。
設備資金
明確に使いみちが決まっていて、その中身が、機械、車、不動産ならば設備資金になります。
運転資金より、使いみちが決まっているので、状況によっては運転資金より貸してくれることもあったりします。
(最終は、企業が返せるかどうかで判断してるでしょうけど)
基本的には、金額が大きめで、期間が長いです。(20-30年といったものもあります。)
基本的には融資は企業が返せるかどうかですが、不動産を購入する場合、その不動産の担保価値も
加味して融資してくれます。
どっちが優位ってことではなく、使う用途に応じて借りていくのが基本となります。
お金の動きがわからない。
2021/06/21なんかしらんけどお金が減っている・・・。
というセリフは若い経営者からはよく聞く話です。
いや、アホみたいに交際費使ってますよ(最近少ないですけど)というわかりやすい場合は
話せば、納得はしてくれますけど。
そんな、損益計算書上以外で影響している場合、残りは貸借対照表で見ます。
資産の増加
現金が減っている場合、基本的にはなにか使ってるわけです。
・固定資産の購入
・売掛金の増加
など資産の金額の増加が原因になっていることがあります。
売掛金の増加がなぜ?という話ですが、売上が上がると損益計算書上は利益が増える計算です。
ですが、売掛金が増えている場合、回収ができてないわけですから、現金ベースでいうと儲かっていない。
なので、その分資金繰りが悪化しているとみます。
負債の減少
あと、損益に見ないものとして、債務の返済があります。
・借入金の返済
・未払金の減少
などです。
通帳を見てたらわかりやすいんですけど、複数の通帳が絡むとややこしいですね。
会計見ていると、こういった数値から計算していきます。
ただし、2期の比較が無いと増加減少はわからないですね。
決算の説明だと、前期の数字になりますけど、先月と今月といった比較も可能です。
そこから、
・固定費
・変動費
・浪費
なんかを探っていきます。
- 2021/06
- 2021/05
- 2021/03
- 2021/02
- 2021/01
- 2020/12
- 2020/11
- 2020/10
- 2020/09
- 2020/08
- 2020/07
- 2020/06
- 2020/05
- 2020/04
- 2020/03
- 2020/02
- 2020/01
- 2019/12
- 2019/11
- 2019/10
- 2019/09
- 2019/08
- 2019/07
- 2019/06
- 2019/05
- 2019/04
- 2019/03
- 2019/02
- 2019/01
- 2018/12
- 2018/11
- 2018/10
- 2018/09
- 2018/08
- 2018/07
- 2018/06
- 2018/05
- 2018/04
- 2018/03
- 2018/02
- 2018/01
- 2017/12
- 2017/11
- 2017/10
- 2017/09
- 2017/08
- 2017/07
- 2017/06
- 2017/05
- 2017/04
- 2017/03
- 2017/02
- 2017/01
- 2016/12
- 2016/11
- 2016/10
- 2016/09
- 2016/08
- 2016/07
- 2016/06
- 2016/05
- 2016/04
- 2016/03
- 2016/02
- 2016/01
- 2015/12
- 2015/11
- 2015/10
- 2015/09
- 2015/08
- 2015/07
- 2015/06
- 2015/05
- 2015/04
- 2015/03
- 2015/02
- 2015/01
- 2014/12
- 2014/11
- 2014/10
- 2014/09
- 2014/08
- 2014/07
- 2014/06
- 2014/05
- 2014/04
- 2014/03
- 2014/02
- 2014/01
- 2013/11
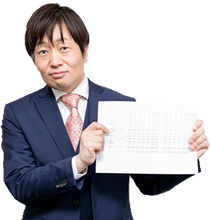
まずはお茶でも飲みに来ませんか?
そして、社長の考える未来と現状を教えて下さい。
税理士に相談!みたいなお固い感じじゃなく、気軽にお茶でも飲みながら、今の経営のこと、将来の夢などを語りに来てください。相談料は不要です。
ご希望の方には、秋口特製の『未来こうなるシート』を後日お送りします。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階 事務所概要はこちら