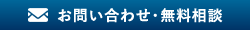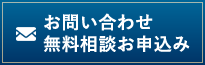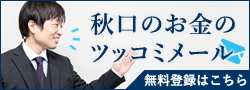事業の倍速コラム。
- 会社売却 2021/06/11 事業承継・引き継ぎ補助金
- 2021/06/10 説明のタイミング。
- 2021/06/09 整える作業。
- 2021/06/08 債務超過会社の売却可能性
- 2021/06/07 規模の差
- 2021/06/04 売り手側と買い手側のズレ
- 2021/06/03 買われる会社
- 2021/06/02 会社の価値とは
- 2021/06/01 M&A
事業承継・引き継ぎ補助金
2021/06/11本日申請が開始した補助金です。
書いているのが日曜だったりしますので、本当にやっているかはわかりませんが
(嘘です。当日アップする前に確認してます。)
詳しくは、以下のサイトを確認してください。
経営革新型
引き継いだ後にする新たな事業に対して補助金が使えるものになります。
経営資源を引き継いだ創業の支援であったり、経営者が交代した場合、M&A後の事業に
つかっていくものですね。
補助率は2/3
最大金額は400万円(創業型・経営者交代型)か800万円(M&A型)、
廃業費用は追加で200万円
といったものです。
専門家活用型
経営資源引継ぎ補助金を引き継いだものです。
M&Aは専門家をつけて行うことが多く、結構な費用がかかったりします。
その費用が中小のM&Aのネックになっていると考えて、その一部を補助するものです。
さて、日曜の時点では「詳細を見る」ボタンが押せない状態ですが、
これをアップする頃には押せるんでしょうか?
⇒押せないですね。ただし要領等はでてきてます。細かいところはともかく
売り手側も買い手側も 補助率2/3 最大400万円みたいです。
細かいことは確認お願いいたします。
なんにせよ、事業承継自体が短期間でできるものではありませんので、補助金ありきでは
動きにくいですね。タイミングが合えばといった要素が多い補助金だと思います。
説明のタイミング。
2021/06/10M&Aは関係者は少なければ少ないほど良いです。
情報が公開されれば通常の業務にも大きく影響する可能性があるからです。
買い手にはあんまりないですけど。
基本はギリギリ。
外部関係者
得意先や仕入先、業界関係者には知られた場合、会社の業績に直接影響が出てきます。
特に得意先に知られてしまうと取引が停止されてしまう可能性も出てきます。
内部関係者
従業員ですね。会社を売った場合、従業員の雇用の継続を望むのは売り手も買い手も同じです。
従業員はいらないという買い手は少ないです。
しかし、従業員側になると代表者が変わるのを知られると何故か不利益になることを決めつけて
他に転職してしまう人が出てきます。基本的には条件変更なしの継続雇用であることが多いのですが
(買い手側の条件のほうが良いことも多いので)
人は変化に過大な不安を感じますので。
悪影響をあることが多いので、基本的にはギリギリというか、譲渡契約が終わってから話すことが多いです。
状況に応じては・・・
M&Aのキーマンについては、譲渡契約の要になることも多いので、最終局面で確認することがあります。
外部関係者には譲渡の話をして、譲渡後も継続取引のお願いにいく。
従業員の中でもキーマンには譲渡後も継続して働いてもらうようお願いする。
本当に大事な部分になりますので、時期も含めて慎重に進めていきます。
整える作業。
2021/06/09何かを売る場合に、きれいにして買いやすい状態にする必要があります。
前回に書いた債務超過であれば、簡単にできるものではありませんが、
会社の整理整頓という作業であればできることから始めていくことになります。
不要なものの処分
設立して期間がたっている場合、不要な部分が必ず出てきます。
実際のものであったり、会計の数字だけ残っているものも含めるとかなりの量になります。
個人的なもの、実際に無いものは処分していっても大丈夫です(税金面は注意)
売る場合に、相手に取っては不要なものですので、そこに価値を見出す買い手はいません。
株主の整理
今では会社は株主1人=代表1人が当たり前にできていますが、
昔は発起人(会社を作ると言った人)が7人必要であったり、会社の事業の途中で株主が増えたり分かれたりと
気がついたら、誰が株主かもわからない。
冗談のような話に聞こえるかもしれませんが、これが意外と多いもの。
通常の会社の経営では問題になることがない場合も(いや、どっかで問題になると思うのですけど)
会社の売却の場合、株式の全てを譲渡することが多いのでまず集める作業から始めます。
利益関係がはっきりしていませんので、あまりに広範囲に株主が広がっていれば、
専門家に整理してもらう作業になります。
何事にも言えますけど、まずは身支度から始めます。
債務超過会社の売却可能性
2021/06/08会社を売却する場合、価値があればあるほど、高くなる。
市場原理まんまの話ですが、それは事実です。
後は、見えない売る側・買う側の諸事情で変わっていきます。
債務超過の会社の場合はどうなるでしょう?
1円以下の金額で商品を売ることはできません。
無償で渡すことはできても、相手が受け取ってくれるかは別問題です。
売れる部分だけ売る。
廃業であれば、残った商品・備品等を処分して終わります。
足元を見られて買い取られるので値段は厳し目です。
しかし、事業譲渡として事業のみを販売する場合、
得意先の一覧や売上口座、実績、そこに関連する従業員が商品になります。
(実際に人を売買するわけではありません。従業員の雇用の継続です。)
ノウハウのような見えないものも価格にはいりますので、廃業と違い、
目に見える物の処分より高くなる傾向にあります。
買う側に債務超過以上の可能性がある。
簡単ではありませんが、買うことで
・収益が飛躍的にあがる
・コストが飛躍的に落とせる
可能性があれば、M&Aの可能性が無いわけではありません。
この「飛躍的」部分が、時間・費用的にどれだけ価値があるかによるので、完全に相手依存の話ですが。
いずれにしろ、そのままでは廃業ではなく倒産になる会社ですので
自己再生の努力が必須になります。
規模の差
2021/06/07通常ネタが困っているので、なにか希望があれば連絡くださいませ。
とそれはさておき、今週もM&Aネタです。
M&Aは基本的に買う側のほうが規模が大きいです。
規模の大きい会社のほうがお金を持っているというのが一番の理由なんですけど。
従業員数
人がほしいから、会社を買いたい。
という理由もよくある話なんですが、なぜか自社の従業員の3割ぐらいを望まれることが多いです。
大量にこられても管理できないということなんでしょう。
乗っ取られるイメージもあるらしいですが。
ある程度大きい会社になってくると、完全に別で管理するので気にされないことが増えてきます。
売上規模
業種によって、利益率が大きく変わってくるので売上高だけで規模がわかるわけではないのですが
買う側は売る側の5倍以上の売上規模であることが多いです。
これは譲渡金額を払うときに
1)払える規模
2)リスクヘッジできる規模
3)すぐに用意できる規模
がそのぐらいの差である。
といったものです。
上記は、あくまで「そういった場合が多い」だけです。
規模が逆転することも、同規模であることも色々あるので、決めつけて考えるわけにはいかないです。
売り手側と買い手側のズレ
2021/06/04売り手側と買い手側では考え方が違います。
それは仕方ない部分もありますので、交渉するときに詰めていきお互いの合意を求めていく形になります。
しかし、価格に関する差異が大きい場合は基本的には埋まることもなく終わることが多いです。
その中には、買い手側として出せる限度額であったり、売り手側としてその金額以上でないと
今後困るといったこともありますが、考え方の違いではなく、考え方の間違いからくるものもあります。
売り手側の勘違い
・商品の経営者自信が考えている価値を主張する。
実際に今の経営者で売れていないのであれば、それは売れていないので価値はないです。
・相手のシナジー効果を価格にプラスする。
相手に自分の事業を足せば、現在の売上ではなく、もっと上がるから価値は高いはずだ・・・
相手はそれを狙って購入しようとはしていますが、それは相手の努力の結果出てくるものであって
いま売り手側が出している成果ではないので価格に足せるものではありません。
売り手側の価値は、あくまで今の現状での価値でしかありません。
未来出るであろう価値は、買い手側が購入した場合のものですので。
売り手側が出せるのであれば、結果を出した後に売ればいいだけです。
買い手側の勘違い
・買い手側が売り手側を判断する。
間違ってはいませんが、売り手側も買われる相手を決める権利はあります。
M&Aの売り手の殆どは60歳以上の経営者です。プライドを持って何十年と経営されてきた方が多いので、
誠意がない人は、最初に切られてしまいます。
・引き継いでもらえるので、安いという勘違い。
時にはそのような場合もありますが、一般的には経営者の最後の商売になります。
そんなにお金はいらないとはいうものの、老後の不安も出てきますので安く買い叩けるようなことはほとんどありません。
書籍に「小さい会社を○○万円で買え」みたいなものもあったかと思いますが、安い会社には安い理由が、
高い会社には高い理由があります。
買われる会社
2021/06/03今、売れている会社は何?
と聞かれていることがあります。
売れてる会社がいい会社とは限りませんが、業界的に売買が多い業種はあります。
それは、流行りであったり、売却金額(購入金額)がわかりやすいといったものです。
しかし、買う側の基準は以下の2つであることが多いです。
興味のある事業
次に書くシナジー効果が高いからといったことも、興味の理由にはなるのですが、
純粋に経営者が次にしたいこと、といったものが多いです。
・飲食に興味があれば飲食(居抜き物件を探すような感覚の人もいます)
・今儲かっていそうな業種
・許可・資格の必要な業種(許可だけがほしいといった事も多いです)
買い手側の業種とは関係無いことが多いので、ほしいと言われる事業の範囲が広かったりします。
売り手側としては、買い手が事業を買ってから、ちゃんとやってくれるのだろうかと不安になることもあります。
シナジー効果が高い事業
買い手側の、仕入先・外注先・得意先・同業の業種であることが多いです。
買い手側も事業の内容について詳しいことが多いですし、売り手側も買われる理由がわかりやすいので
従業員等への説明もしやすいです。
ただ、売り手側が買い手側を知っていた場合、拒まれる可能性もあります。
秘密保持契約(お互い外部に言わないという約束)をしていたとしても、例えばそもそも得意先であったり
ライバル会社であった場合は避けたいと思われることが多いです。
興味のある会社を購入することが悪いわけではありません。自社の業界に限界を感じているのであれば
他の業界に行くこと自体は普通にあることですし、そのときにM&Aでうまく外の業界の会社を買うことができるのであれば、
時間と費用を大幅に削減することができるからです。
会社の価値とは
2021/06/02会社を売却する場合に、買い手が業種等の次に確認するのは価格です。
いくらいい会社であっても、購入資金が足りなければ、交渉することができないからです。
しかし、売り手側も明確な売却価格を決めていないことも多かったりします。
売る価値があるかすらわからないと言った場合もあります。
資産の時価評価
会社の貸借対照表を基準として、時価評価していきます。
例えば
・売掛金に回収不能なものはないか
・在庫は正しいか
・保険の現在解約した場合の金額はいくらか
・貸借対照上にのっていない資産・負債はないか
といったものを探して評価してきます。その結果資産と負債の差額がプラスであれば
差額分価値がありますし、マイナスであれば価値がないという判断ができます。
稼ぐ力の評価
会社の損益計算書を基準として、評価していきます。
・損益の中でイレギュラーなものは無いか
・過大な役員報酬はないか
といったものを積み上げていき、プラスであれば価値がでてきますし、
マイナスであれば価値がないといえます。
資産の時価評価と違って、プラスであれば、そこに1-3年分をかけることで稼ぐ価値を評価していきます。
資産の価値・稼ぐ力の価値を単純に足す場合もあれば、業種によっては片方だけの評価で計算することも。
あくまで上記の評価を基準に考えていきます。
最終は、売り手側・買い手側の状況次第ですので、あくまで基準といった考え方になります。
M&A
2021/06/01事業を次に繋げる時の最後の手段ですね。
親族でもなく従業員でもない。全くの第三者に売却するものです。
昔は、得意先や仕入先、知人に売ることが多かったかと思いますが、今は市場が確立されてますので、
全く知らない第三者に売却することも多くなってきました。
M&A自体が一般的になってきたとはいえ、まだまだわかりにくいものだとは思います。
手段はいくつかあるのですが、基本的なものは次の2つ。
株式譲渡
イメージするまんまではないでしょうか?
会社の株式を買い取って、その会社を所有する形になります。
会社のすべてを買い取るので、資格とか許可といったものが引き継がれる形になります。
(旧代表の資格に依存していると別ですけど)
ただ、決算書上に見えていない負債も引き継ぐことになりますので、譲渡前には会社の中身を
正確に確認する必要があります。(デューデリジェンスと言います)
事業譲渡
会社の一部分を購入する形です。
なので、上記と違い、購入する部分だけ確認することになりますので、チェックは株式譲渡より
簡単になります。
ただし、一般的には許可や免許は再取得する必要がありますし、契約も再度契約をしなおす
必要がでてきます。
どっちも一長一短ではありますので、売り手側・買い手側の状況に応じて選んでいくことになります。
- 2021/06
- 2021/05
- 2021/03
- 2021/02
- 2021/01
- 2020/12
- 2020/11
- 2020/10
- 2020/09
- 2020/08
- 2020/07
- 2020/06
- 2020/05
- 2020/04
- 2020/03
- 2020/02
- 2020/01
- 2019/12
- 2019/11
- 2019/10
- 2019/09
- 2019/08
- 2019/07
- 2019/06
- 2019/05
- 2019/04
- 2019/03
- 2019/02
- 2019/01
- 2018/12
- 2018/11
- 2018/10
- 2018/09
- 2018/08
- 2018/07
- 2018/06
- 2018/05
- 2018/04
- 2018/03
- 2018/02
- 2018/01
- 2017/12
- 2017/11
- 2017/10
- 2017/09
- 2017/08
- 2017/07
- 2017/06
- 2017/05
- 2017/04
- 2017/03
- 2017/02
- 2017/01
- 2016/12
- 2016/11
- 2016/10
- 2016/09
- 2016/08
- 2016/07
- 2016/06
- 2016/05
- 2016/04
- 2016/03
- 2016/02
- 2016/01
- 2015/12
- 2015/11
- 2015/10
- 2015/09
- 2015/08
- 2015/07
- 2015/06
- 2015/05
- 2015/04
- 2015/03
- 2015/02
- 2015/01
- 2014/12
- 2014/11
- 2014/10
- 2014/09
- 2014/08
- 2014/07
- 2014/06
- 2014/05
- 2014/04
- 2014/03
- 2014/02
- 2014/01
- 2013/11
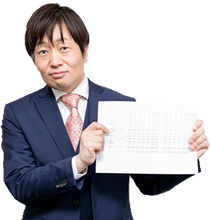
まずはお茶でも飲みに来ませんか?
そして、社長の考える未来と現状を教えて下さい。
税理士に相談!みたいなお固い感じじゃなく、気軽にお茶でも飲みながら、今の経営のこと、将来の夢などを語りに来てください。相談料は不要です。
ご希望の方には、秋口特製の『未来こうなるシート』を後日お送りします。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階 事務所概要はこちら