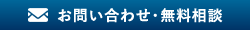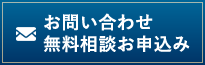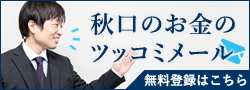事業の倍速コラム。
- 財産管理 2021/06/18 次世代につなげる資産の運用・管理とは
- 2021/06/17 任意信託
- 2021/06/16 遺言書と成年後見。
- 2021/06/15 元気じゃなくなった時に・・・
- 2021/06/14 不動産がメインの場合。
- 2021/05/21 どうして独立したのか。
次世代につなげる資産の運用・管理とは
2021/06/18今持っている資産をできれば次の世代についでもらいたい。
特に先祖代々そうしてきた場合の思いは強いものです。
しかし、時代は変わってきています。
昔のように、長男が全ての責任と財産を継ぐと言うことは厳しくなってきています。
自分の思いと、周りの思いを繋げる。
昔は、先祖がしてきたことをそのままなぞらえても上手くいくことが多かったと思います。
今は、10年前の方法ですら、間違った方法になってしまう時代になっています。
それだけ、環境が目まぐるしく変わってきているわけです。
子孫のために自分がしてきたことが、良いか、悪いか。
それはわかりませんし、変えることはできませんが、今からの行動は変えることができます。
今だけ得する方法、ではなく、子孫の将来に向けて有効な手段を取る必要があります。
今、考えられる最大の事とは。
このページを読んで、真剣に考えたいと思われた人に必要な最大な事とはなにか。
それは・・・
「今すぐ相談し、有効な方法を実行すること。」
の一択になります。
急かせてるようでいい気分ではないとは思いますが、
ざくっと言えば
「ボケる前に動かんと、できることがなくなってくる。」
という現実があるからです。
人間いつかボケるもの(今のところですけど、薬は開発されるかもしれませんね)
ボケはいつやってくるか、どの程度進行するのか誰もわからない。
だから、自由に動ける今の間に、行動しないといけない。
となってくるわけです。
まずは、詳しい人に相談を。
親が認知症になって・・・ってスタートが当事務所に来られる最初の相談だと・・・
できることって限られてきますので。
任意信託
2021/06/17任意信託とは、本人(委託者)が、誰か(親族が一般的:受託者)に依頼して、行動してもらうものです。
1)本人が亡くなるまで、子供に管理してもらって、本人が亡くなったときには子供に贈与(相続)する。
2)預かったお金を定期的に、障害のある子どもに渡してもらい、子供が亡くなったら、残ったお金を受託者に贈与する。
なんてときに使ったりします。
信託の意味があるの?
1)を聞いても
「別に信託してなくてもできるんじゃないの? 最後は遺言書かかないと揉めるかもしれないけど。」
と反応されるかもしれません。
たしかに、本人が認知症になっていなければ、問題なくできることです。
しかし、認知症を患ってしまうと、管理のうちで
・大きな修繕に伴う出金
・立替
・不動産の売却・購入
といったものができません。
成年後見であっても、不動産の買い替えといったものは困難です。
ハードルの高さ
他にも色々使いみちがあるわけですが(HP内にも書いてありますので暇なときにでも見てくださいね)
知らない人がほとんどだと思います。
2)については信託銀行が商品として提供しているものに似ていますので、知っている人もおられますけど。
すごくざっくりいうと、任意信託とはしてほしいことをまとめた契約書です。
ちゃんと依頼主の思いに沿ったもので、なおかつ問題がおこらないものを作るといった契約書が
作れる人が少ないという問題。
言われる通り書くなら、できるでしょうけど、
・思いからあまりずれない。
・契約として問題がない。
・漏れがない。
・税金が予想以上に出ない。
といった条件をクリアさせるのは、なかなか至難の業です。
あと、現金を預かるときに「信託口口座」といったちょっと変わった口座を作れる銀行が少ない。
といった色々ハードルがあるものの、使う価値は十二分にあるものだと思います。
そういった財産があれば・・・ですけど。
遺言書と成年後見。
2021/06/16如何に自分が健康なうち、判断がはっきりしているうちに行動すべきか。
前回はそういった事を書いたかと思います。
その中で、一般的な方法をいくつか書いてみます。
遺言書
自分の財産を誰に渡したいかを記載するものです。
判断能力がなくなってしまうと、作成することができません。
自分が亡くなるまでは有効性はありません。
誰に渡したいか。
法定相続人に対するものがほとんどですが、
息子さんの奥さんやお孫さんといった、法定相続人以外も対象にすることができます。
税金面や遺言書執行後に相続人間のトラブルにならないように配慮する必要があります。
成年後見(任意後見)
本人の判断能力が不十分な時に、申立により家庭裁判所によって選任された後見人等が
本人に代わって財産や権利を守り、本人を法的に支援する制度です。
財産を守るというのが第一ですので、資産を譲渡等については一定の条件が付くことが多いです。
例えば、介護施設に入居するために不動産を売却するなどです。
家庭裁判所の判断を仰ぐ必要があるので、自由に売買ができるわけではありません。まだ判断能力があるうちに、後見人を指定する制度を任意後見といいます。
主に司法書士さんの分野ですね。
税理士として手伝うとしたら、実行時にどのぐらいの税金がかかるか
を確認することが多いです。
明日は、まだまだ一般化はしていないですが、もう一つの手段である任意信託について
書いてみたいと思います。
元気じゃなくなった時に・・・
2021/06/15体力がある時には問題がないことも、何かあった場合は・・・色々問題が出てきます。
体の問題
発病し入院となった場合、経営者には代わりがいません。
・本人抜きでどれだけ事業を運営できるか
・収益が下がった場合に、補填できる手段を作っているか
と言った対策を元気な間にしておく必要があります。
一般的には、自分の右腕となる人間を育てるとか、仕組み化、何かしらの保険や、余裕を持った借入で
対策していく事が多いです。
認知の問題
本人の判断に問題が出てくると
1.本人の行動に問題が出てくるので、経営どころではなくなる
2.周りが対応しようにも、本人の判断ができないなら、株・不動産等の処分、移動ができず身動きが取れなくなる。
と言った事が起こります。
1.は体の問題より大きな影響が出てきますし、2に至っては、改善にようにも身動きが取れなくなります。
老化と認知の問題は本人も認識していますが、体の問題のように、病気で入院したと言ったような自覚が出てくる事は稀です。
ついつい、後手になりがちです。
対策として、あげられているのは、
・遺言
・成年後見
・信託
と言われるものです。
それぞれの特徴は次回に書いてみたいと思います。
(ちなみに、得意な士業は、弁護士や司法書士になりますので、あくまでざっくりですが)
不動産がメインの場合。
2021/06/14経営者が事業の引き継ぎ相手がいない場合、廃業か売却か従業員への引継ぎか。
畳むか、外部への委託になります。
では、親族への引継ぎができそうな場合にどうすべきか。
特に不動産賃貸業のように、経営自体が他の業種に比べて容易な場合(現状維持の話ですけど)
引き継ぐ事を事前に詳しくは語っていません。
借入について
現状の借入についてではなく、元経営者が高齢の場合、これから借りる借入については
継ぐ人間が返済すべき借入になります。
高齢であっても、不動産担保があるので融資自体ができない事はないかもしれません。
しかし、不動産関係の事業を引き継ぐ場合、個人であっても、法人であっても、引き継ぐ時に
多額の税金が発生する可能性は高いです。
借入をした場合、相続する税額自体は下がるのですが、不動産ばかりで現金がなかった場合、
税金が払えないから、結局不動産を売却する可能性が出てきます。
誰に引き継がせるのか
個人で不動産を持っている場合、誰に引き継がせるかも明確にしておく必要があります。
不動産を先祖代々持っている場合、すでに兄弟で共有名義である事も出てきます。
兄弟ぐらいであれば、意思疎通もできているので(昔は特に長男の意見が通りやすかったので)
共有にしていても問題がなかったかもしれませんが、その子供たちになってくると
・人数が増えてくる
・誰が管理するかが不明瞭になる。
と問題が出てきます。
複数あるのであれば、事前にどれを誰に継がせるのか。
共有名義のみであるなら、事前に共有をなくす(購入等)する事ができないか
など、対策をしておく必要があります。
今の所有者より、未来の所有者の方が難易度が上がるからです。
最後に、自分の資産とはいえ勝手に行動すると、最後に困るのは親族ですので
行動する前に考えて欲しいと思います。
どうして独立したのか。
2021/05/21今回は初心に戻って、なぜ独立したのかを考えてみたいと思います。
初心に戻れば、今の状況を考え直すきっかけになるかもしれませんし。
会社を起こす最初きっかけはいろいろですが、漠然としたイメージでよくあるのは
・お金に困らない生活がしたい
・時間に縛られたくない
といったものです。
どのレベルのお金であれば困らないのか
どんなふうに時間を過ごしたいのか
は人それぞれですが。
お金に困らない。
会社員の人でも高給取りと一般的に言われる人でもお金にゆとりがあるかといえばそうではありません。
見た目はお金持ち感が溢れていますが、お金を使う人とのお付き合いが増えるので、出費が収入を超えてしまうのです。
・家
・保険
・教育費
この全てを最高レベルを・・・となると会社員ではなかなか厳しいかと思います。
一般的には年収1000万円でも厳しいとは言われています。
逆に、出費より収入が多ければ困ることはありません。
会社でも一緒ですけど、いかに収入までで抑えるか、抑えていれば困ることにはなりません。
時間に縛られたくない。
経営者は時間に縛られていないか?
会社には長時間いないかもしれませんが、会社でも家でも24時間仕事のことを考えているのが経営者です。
無自覚でも考えている。
そういった人種ですので、時間に一番縛られているかもしれません。
が、どのように時間を使うかを決めるのは経営者自身です。
会社員であれば、最低でも勤務時間は会社の指示に従う必要があります。
忙しくしていても、ボーッとしていても、自分の意思で決めたのであれば縛られていないと考えられますね。
自分を振り返ってみてどうだったでしょうか?
お金に困っているという意味を履き違えてませんか?
ちゃんと時間を自由に使えてますか?
もし、それでも違っているなら、そこから変える必要がでてきますね。
- 2021/06
- 2021/05
- 2021/03
- 2021/02
- 2021/01
- 2020/12
- 2020/11
- 2020/10
- 2020/09
- 2020/08
- 2020/07
- 2020/06
- 2020/05
- 2020/04
- 2020/03
- 2020/02
- 2020/01
- 2019/12
- 2019/11
- 2019/10
- 2019/09
- 2019/08
- 2019/07
- 2019/06
- 2019/05
- 2019/04
- 2019/03
- 2019/02
- 2019/01
- 2018/12
- 2018/11
- 2018/10
- 2018/09
- 2018/08
- 2018/07
- 2018/06
- 2018/05
- 2018/04
- 2018/03
- 2018/02
- 2018/01
- 2017/12
- 2017/11
- 2017/10
- 2017/09
- 2017/08
- 2017/07
- 2017/06
- 2017/05
- 2017/04
- 2017/03
- 2017/02
- 2017/01
- 2016/12
- 2016/11
- 2016/10
- 2016/09
- 2016/08
- 2016/07
- 2016/06
- 2016/05
- 2016/04
- 2016/03
- 2016/02
- 2016/01
- 2015/12
- 2015/11
- 2015/10
- 2015/09
- 2015/08
- 2015/07
- 2015/06
- 2015/05
- 2015/04
- 2015/03
- 2015/02
- 2015/01
- 2014/12
- 2014/11
- 2014/10
- 2014/09
- 2014/08
- 2014/07
- 2014/06
- 2014/05
- 2014/04
- 2014/03
- 2014/02
- 2014/01
- 2013/11
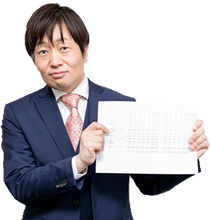
まずはお茶でも飲みに来ませんか?
そして、社長の考える未来と現状を教えて下さい。
税理士に相談!みたいなお固い感じじゃなく、気軽にお茶でも飲みながら、今の経営のこと、将来の夢などを語りに来てください。相談料は不要です。
ご希望の方には、秋口特製の『未来こうなるシート』を後日お送りします。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階 事務所概要はこちら